
市民後見人
市民後見人とは
岩間伸之「『市民後見人』とは何か- 権利擁護と地域福祉の新たな担い手」『社会福祉研究』第113号, 鉄道弘済会, 2012年、P13
大阪市の市民後見人活動
【大阪市市民後見人ロゴマークについて】
後見人を意味する Guardian の頭文字のGとハートをモチーフにしています。
グリーンのモチーフは手を差し延べ、判断能力が不十分な方を支援している様子を表しています。
大阪市市民後見人活動啓発動画
あらすじ
市民後見人の広報・啓発のため、大阪市社会福祉協議会と大阪府社会福祉協議会が共同で制作したショートムービーです。実際に市民後見人として活動している皆さんにご登場いただいています。
あらすじ
吉本さくら(63歳)は、家庭裁判所に選任され、上田澄子(87歳)の市民後見人になりました。高齢で一人暮らしの上田澄子の財産管理と、その生活を見守るためです。ところが、テレビの音が大きいことや、認知症が進み外出すると自宅に帰れなくなることが時折あり、それが近隣の苦情につながっていました。市民後見人として本人を支え、どのように近隣の理解を広げ、本人の生きがいを生みだしてゆくのか…吉本さくら市民後見人の奮闘のドラマです。
市民後見人の声

週1回、ご本人が通所されている作業所を訪問しています。施設の指導員さんと情報交換した後、本人とお話ししています。金銭管理については、ほとんど口座引き落としを利用し、月2万円程度のお小遣いだけ施設にお預けして管理してもらっています。土日はガイドヘルパーを利用し、映画やカラオケ、買い物に行けるように手配をしてもらっています。本人は外出が好きで、どこに行くのもとても喜ばれます。
後見活動では養成講座で教えてもらったように、他人のお金を預かることの責任の大きさを理解し、活動の記録をしっかりとることを心がけています。
後見人になった直後は、施設との引継ぎ、区役所や銀行での手続き、成年後見支援センターでの専門相談などに時間を要しますが、私はフルタイムで働いているため、平日の日程調整や期限の決められている書類作成が大変でした。ただ、センターの丁寧なフォローがありますし、初動期さえ乗り越えれば、仕事の合間や休日を利用して自分のペースで活動ができています。後見活動は家庭裁判所に報告するための日々の記録や書類をきちんと整理することが大切だと思います。

後見人にならなければ絶対に出会わなかった人に出会い、その人の人生に関わっていることのうれしさがあります。仕事上の肩書での付き合いではなく、一人の人として相手に必要とされていることは、責任は大きいですがやりがいと感じているところです。
本人はお話でのコミュニケーションは得意ですが、文字を読んだり書いたりすることができません。本人も新たに読み書きを習得することはあきらめていました。しかし作業所の職員さんが「後見人さんに頑張っていることを伝えたらきっと喜ぶと思うよ」と言うと本人は「頑張る!」と一生懸命文字を書く練習をしていると聞きました。
本人は褒められることが好きな方です。職員さんは立場上、どうしても利用者の「皆さん」という対応になると思います。特に、身寄りのない方は「あなた」として認めてくれる存在が大きいのだと思います。市民後見人は「あなた」に寄り添う活動であり、それが伝わるとご本人の生活も変わってくると思います。
大阪市の市民後見人は歴史があり、他にはない先駆的な活動をしています。完全なボランティアでここまでできるのは大阪市の自慢だと思います。一人の住民として地域の支え合いに参加してみませんか?

当時は成年後見制度そのものを知らなくて、仕事の研修で初めて成年後見制度という言葉を知りました。ちょうどその頃、身内が認知症の診断を受け、学んだばかりの後見制度を調べると、市民後見人というものがあることを知り、これもまたタイミングよく養成講座の募集期間だったので受講にいたりました。
市民後見人として活動することに対して不安はありましたが、成年後見支援センターのバックアップがあったので安心して受諾しました。当初はしょっちゅうセンターに電話していたと思います。
専門職の先生方やセンターから後見活動についてたくさん助言をいただきましたが、初めて本人にお会いする時は緊張しました。初回はいろいろな支援者が同席してくれますが、2回目以降は「自分一人で訪問しなければならないが大丈夫か」という思いがありました。養成講座で「コミュニケーションが上手く図れなくても訪問して本人に寄り添っているだけでいい」と教えてもらったのが励みになりました。

その人の人生の最期に自分は何ができるのだろうかと考えています。
十数年前、自分の父の様態が悪くなり病院で亡くなりました。入院してわずか20日でした。お酒が好きだった父親。好きなことを我慢して慣れない場所で最期を迎えさせてしまったことに後悔が残っています。
お金や健康だけではなく、本人にとって何が幸せなのかを考え、住み慣れた場所での暮らしを大切にしたいと思っています。
ある日、職場にどら焼きがひとつ余っていたので、何気なしに本人に持って行きました。すると、飲み込むかの勢いで一気に食べられ、実は大の甘党であったことを知りました。それからカステラやバームクーヘンなどを持参するようになり、今では後見人のことを甘いものを持ってきてくれる人という認識になっています。
市民後見人がいなければ、本人の好みはわからなかったと思うし、これだけ好きなものを食べることもなかったのではないかと思います。
市民後見人養成講座を受講しようと考えている人は、何か人の役に立ちたいと思っている人だと思います。後見活動を通して一般人の自分でもできることはたくさんあると感じました。
大阪市には同じような思いをもつたくさんの市民後見人がいます。センターのバックアップもあります。地域に貢献したいと思っている人はぜひ受講を!
活動のしくみ

「市民後見人バンク」への登録
大阪市成年後見人等候補者検討会議に候補者を推薦
家庭裁判所が選任
市民後見人の後見活動サポート
養成・支援
大阪市成年後見支援センターでは、市民後見人養成講座を開催するとともに、受任調整や選任された市民後見人への活動支援を行っています。バックアップ体制を整えることで、常に安心して市民後見人活動に励んでいただくことができます。
日常的な相談
センター相談員が、市民後見人の相談に日常的に応じ、必要に応じて専門相談につなぎます。
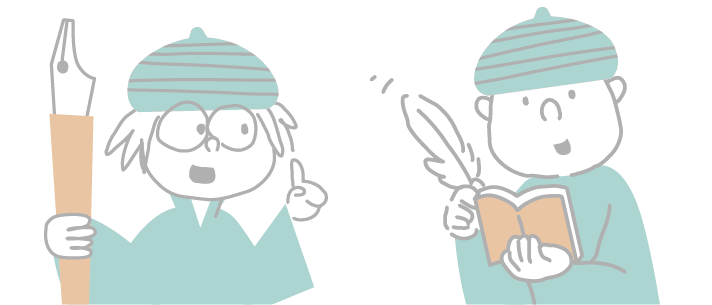
専門相談(弁護士・司法書士・社会福祉士)
初動期打ち合わせ
1か月目財産目録提出前
3か月目
6か月目の家裁への報告前
その後半年ごとの家裁への報告前に専門相談実施
その他課題が生じた時必要に応じて専門相談を受けられます

大阪市市民後見人連絡協議会